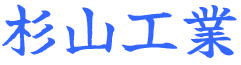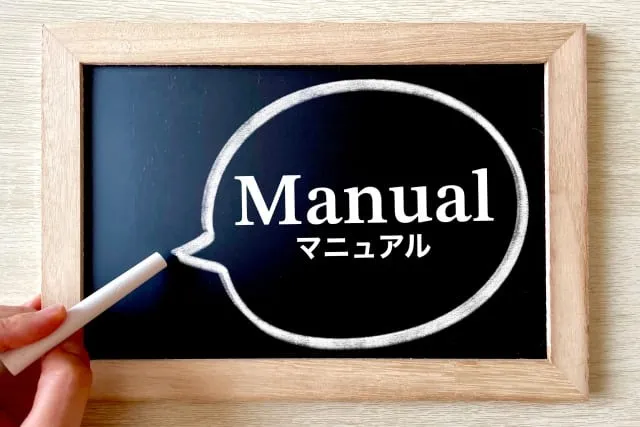雨樋工事の耐用年数とは?交換のタイミングや長持ちさせるコツ
2025/04/10
こんにちは!杉山工業です。私たちは神奈川県南足柄市に拠点を構え、屋根の板金工事からカバー工法、屋根の葺き替えや屋根塗装など、屋根に関する幅広いサービスをご提供しております。本日は、雨樋工事の耐用年数についてお話していきます。住まいを守るうえで欠かせない存在になるのが雨樋です。普段はあまり意識することがないかもしれませんが、雨樋は建物の外壁や基礎部分を雨水から守るための重要な役割を果たしています。ここでは、雨樋工事の耐用年数や交換のタイミング、長持ちさせるコツなどについて紹介していきます。
目次
雨樋工事の耐用年数
種類ごとの耐用年数を紹介
塩化ビニール
塩化ビニール製の雨樋は安価で軽いという魅力の一方で、耐久性の面でみるとやや劣る傾向にあります。時間の経過とともに弾力性が低下し、ひび割れや変色といった症状が出やすいというデメリットがある素材です。日本の一戸建てではよく用いられていますが、耐用年数はおよそ15~20年程度になります。
ガルバリウム
ガルバリウムは亜鉛とアルミ、シリコンを混合して作られたもので、サビに強く耐久性、耐候性の高い素材で軽量という特徴があります。屋根などには使われることが多い素材ですが、雨樋としては費用が割高となるためあまり普及していません。耐用年数はおよそ20~30年程度になります。
アルミ・ステンレス
アルミやステンレス製の雨樋はサビがほとんど発生しないという特徴があるため、雨にさらされる雨樋には向いている素材になります。また熱にさらされても膨張しにくく、変化が少ないという魅力も持っています。しかしアルミやステンレス製の雨樋は価格がやや高い傾向にあり、ラインナップも限らているという難点もあります。耐用年数はおよそ30年程度になります。
銅
同製の雨樋は表面に発生する緑青が酸化を防ぐという魅力がありますが、酸性に弱いという弱点もある素材です。そのため、酸性雨によって穴が開いてしまうリスクがあるのです。しかし耐用年数はおよそ30年と長めになるため、酸性対策をきちんと行うことで長持ちさせることが可能になります。
交換のタイミング
耐用年数を過ぎた雨樋は、外見上問題がなくても内部の劣化が進行している場合があります。特に雨の日に水があふれる、継ぎ目からの漏れ、ひび割れや変形などが見られた時には注意が必要です。また傾きや外れ、雨水の流れる音の変化なども劣化のサインになります。こうした異常を放置すると、外壁や基礎の劣化を招く恐れがあります。台風や大雪の後は目に見えない損傷が起きやすいため、定期的な点検と早めの修理を心がけると良いでしょう。
雨樋を長持ちさせるポイント
・定期的な清掃
雨樋の詰まりは劣化の原因になってしまう可能性があります。落ち葉や砂ぼこり、鳥の巣などが溜まると雨水が正常に流れず負荷がかかり、変形や割れに繋がります。そのため、年に1~2回程度の清掃を行うのがおすすめです。
・早めの補修
軽い破損やズレは、早い段階で補修を行うことで大規模な交換工事を避けることが可能になります。水漏れを見つけたら、放置せず早めに業者に相談すると良いでしょう。
・適切な素材の選定
寒冷地や台風の多い地域など、環境によって適した素材は異なります。地域の特性に合った素材を選ぶことで、より長持ちさせることができます。
まとめ
雨樋工事の耐用年数や交換のタイミング、長持ちさせるコツなどについてお話させていただきました。雨樋は家を雨から守る重要な役割を担っています。素材によって耐用年数は異なりますが、どんな素材であっても定期的な点検とメンテナンスを行うことが大切になってくるでしょう。
----------------------------------------------------------------------
杉山工業
住所 : 神奈川県南足柄市矢倉沢1311
電話番号 : 0465-25-4963
----------------------------------------------------------------------